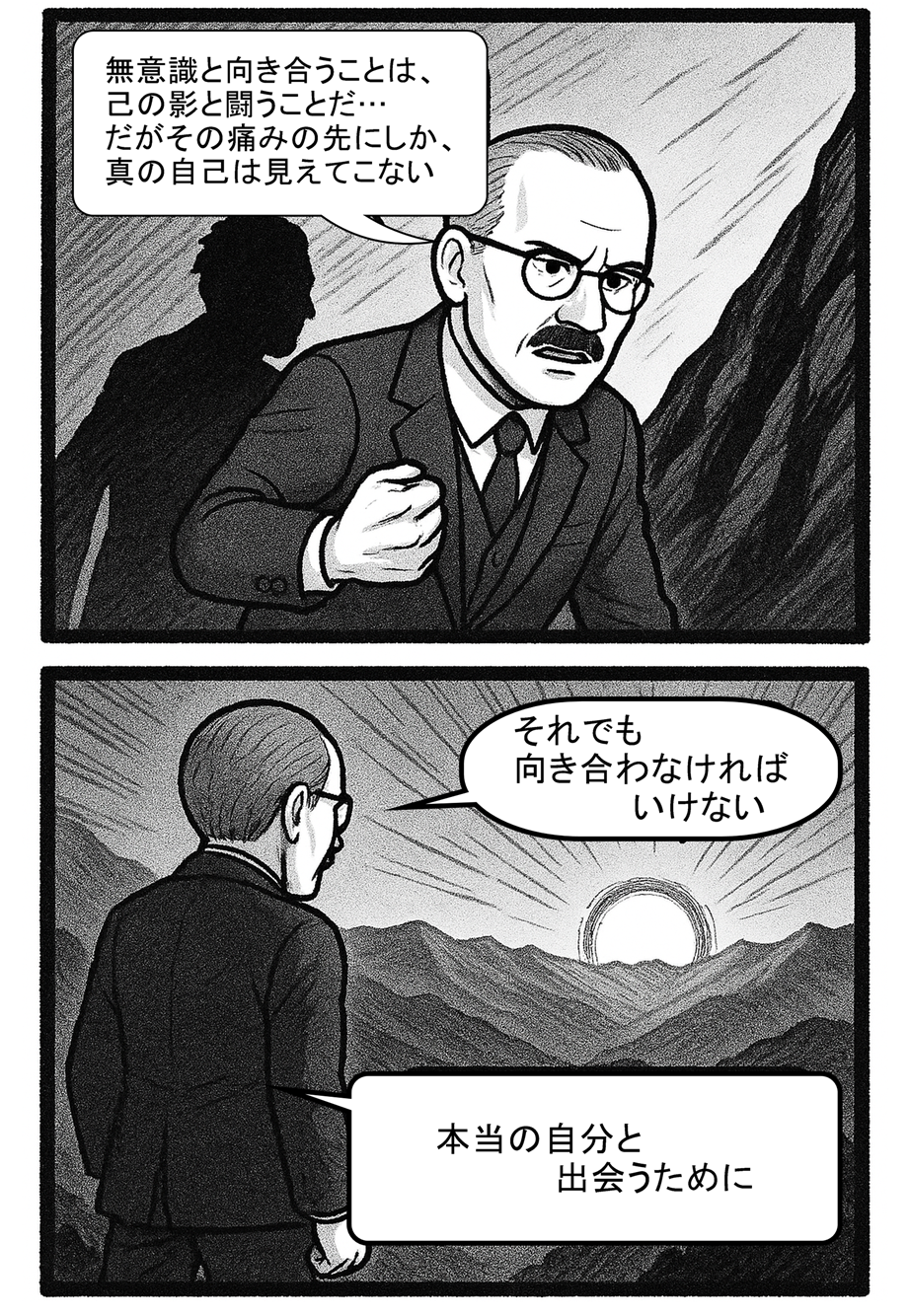🌍自分を知るということは、無意識との対話から始まる
私たちは、本当に「自分」という存在を知っているのでしょうか?
心理学者カール・グスタフ・ユングが生涯をかけて探究したのは、目に見える性格や行動パターンではなく、
その奥にある“もう一人の自分”──つまり無意識の領域でした。
彼は考えました。
「意識だけでは、人間という存在を理解しきれない。
本当の成長は、“心の深層”と向き合うことから始まる。」
この考え方は、MBTIのルーツとなるタイプ論を支える土台でもあり、
ユング心理学の核心をなす「個性化(Individuation)」という概念へとつながっていきます。
🧠シャドウ(影)との対話
ユングが提唱した「無意識」の中には、自分が気づいていない欲求・記憶・感情が眠っているとされます。
そしてそれらは時に「シャドウ(影)」として現れ、私たちの行動や感情に予期せぬかたちで影響を与えます。
たとえば──
- 誰かに感じる過剰な嫌悪感
- 根拠のない不安や怒り
- つい繰り返してしまう失敗や葛藤
これらはすべて、自分自身の“見たくない部分”が無意識下で働いているサインかもしれません。
ユングはこう言いました。
「人は、無意識と対話することでしか、本当の自己を知ることができない」
つまり、成長とは“影を排除すること”ではなく、
それを見つめ、受け入れ、統合していくことなのです。
🌀すべては“統合”のために
ユング心理学のもう一つのキーワードが「統合(Integration)」です。
人は、表の顔と裏の顔、理性と衝動、思考と感情といった、
さまざまな二項対立を抱えた存在です。
たとえば──
- 外向/内向
- 感覚/直観
- 思考/感情
- 善/悪
- 意識/無意識
私たちはつい、「良いもの」だけを選びたくなります。
しかしユングは言います。
「統合されていない“理想の自分”は、むしろ脆い存在である」と。
本当の強さは、自分の中にある矛盾や影をも受け入れたときに生まれる。
それがユングが説いた“個性化”というプロセスでした。
個性化とは、心の断片を拾い集めて「ひとつの自己」として生き直すこと。
それは、痛みを伴うがゆえに、本物の成長なのです。
🪞MBTIは“ラベル”ではなく“鏡”である
MBTIは性格診断ツールとして知られていますが、
その源にあるユングの思想を踏まえれば、それは「自分の無意識に気づくための鏡」であることが分かります。
MBTIによって自分の“心の偏り”を知ることは、
統合の旅において大きな第一歩です。
ただし、それはゴールではありません。
「私はINFPだから」「ESTJだから」
そんなラベルのために使うのではなく、
「私はどんな“心の偏り”を持っているのか?」と問い直すことが、真の活用法なのです。
🔚本当の“自分”と出会う勇気
「自分を知る」ということは、ただ性格を理解することではありません。
自分の中にある“影”や“未成熟な部分”とも向き合う覚悟を持つこと。
そしてそれは、勇気のいる旅ですが、決して孤独なものではありません。
MBTIが「診断ツール」で終わらず、
「人生を変える地図」となり得るのは、ユングのこの思想が背景にあるからなのです。
次回は、MBTIを実際に世に広めた“もう一人の主人公”、
キャサリン・ブリッグスという一人の女性の物語に入っていきます。
「違いは、間違いではない」──
その想いを抱いた母から、MBTIの物語は次のステージへと動き始めます。